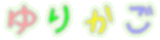 |
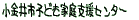 |
|||
| ホーム | 『ゆりかご』って? | information | 予定表 | 関連相談機関 |
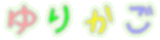 |
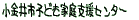 |
|||
| ホーム | 『ゆりかご』って? | information | 予定表 | 関連相談機関 |
| 『ゆりかご』からお知らせ | ENJOYリポート | 写真で見るトピックス | ゆりかご便り | センター便り 巻頭言から |
2005年11月〜2012年1月号のゆりかご便り 巻頭言から |
ここには、支援センター便り『ゆりかご』(季刊)から、
ゆりかご元責任者 宮澤陽子さん、芹澤政子さんの巻頭言を抜粋して載せています。
子どもたちや親御さんへのあたたかいメッセージが沢山詰まっているこのページをどうぞよろしく!
[バックナンバーは下へスクロールして下さいネ!]
2012.1.25 発行 №33より
| 「子どもについて」 ジラーン作 神谷恵美子訳 赤ん坊を抱いた一人の女が言った。どうぞ子どもたちの話をして下さい。それで彼は言った。 あなたがたの子どもは あなたがたのものではない。 彼らは生命そのもののあこがれの息子や娘である。 彼らはあなたがたを通して生まれてくるけれども あなたがたから生じたものではない。 彼らはあなたがたと共にあるけれども あなたがたの所有物ではない。 あなた方は彼らに愛情を与えうるが あなた方の考えを与えることはできない。 なぜなら彼らは自分自身の考えをもっているから。 あなたがたは彼らのからだを宿すことはできるが 彼らの魂を宿すことはできない。 なぜなら彼らの魂は明日の家に住んでおり、あなた方はその家を夢にさえ訪れられないから。 あなた方は彼らのようになろうと努めうるが、彼らに自分のようにならせようとしてはならない。 なぜなら生命は後ろへ退くことはなく いつまでも昨日のところにうろうろ、ぐずぐず、してはいないのだ。 あなた方は弓のようなもの、その弓からあなた方の子どもたちは生きた矢のように射られて、 前に放たれる。射る者は永遠の道の上に目的を見さだめて、力いっぱいあなた方の身をしなわせ その矢が速く遠くとび行くように力をつくす。射る者の手によって 身をしなわせられるのをよろこびなさい。 射る者はとび行く矢を愛するのと同じように じっとしている弓をも愛しているのだから。 上記の詩を読む機会がありました。初めに「あなたがたの子はあなたがたのものではない。」 「あなたがたの所有物ではない。」「考えを与える事はできない。」の「ない・ない」の連呼。 産まれ出て愛おしかったり、夜泣きにフラフラになりながら悩みつつの子育て。 自分の一部と思っているからこそ頑張ってこれたのに・・・。 そうか、自分の身から生まれたからと言うだけで、我が子に甘えていたのかもしれない。 愛情を注いでいると言う自分の自負が、我が子の本当の姿を見えなくしていたかもしれない。 そう思ってこの詩を読んでみると、子どもの命・生きる力・親でありながらも 子どもの世界を見守る事の必要性を感じました。 親であるがゆえに子どもの世界に土足で踏み込んではいけない事もあるのでしょうね。 時には、親として事の良し悪しを伝える必要もあるでしょうし、親の考えを伝える事も大事ではありますが、 おしつけにならない程度のほど良い関係が出来ると良いですね。 と、言いながらもこの程良さがその子一人一人違うから悩んでしまうのです。 そんな時、ゆりかごスタッフに声をかけてください。答えはみつからないかもしれませんが、 一緒に考えていくことは出来ると思います。 芹澤政子 |
2011.10.4 発行 №32より
| 8月8・9・10日と長崎に行ってきました。9日はおりしも66回目の原爆の日。 幼いお子さん・学生さん・ちょっと華やかなお姉さんからお年を召した方まで多くの方が、 小雨の中を平和祈念公園に向かって長い列を作っておりました。 66年たった今も、この日を覚えて平和への祈りをささげておりました。 その公園の入り口近くに数人の方が石碑の前で祈りを捧げていました。 その石碑には「中国人被爆者の碑」と刻まれておりました。 被爆を受けたのは日本人ばかりではなく、日本にいた多くの外国の方のことを知らされ、頭を垂れる事を 許してもらいました。平和祈念公園の近くには爆心地があり、破壊した多くの瓦礫が地中に 埋めてありました。私たちの知らない世界・時代。多くの方の命の尊さを肌で感じた長崎でした。 東日本大震災で被災した高校生が、9日の長崎を訪ね、被爆地にいた女性から原爆の様子を聴いている 番組を偶然見る機会がありました。被爆にあった当時幼かったその方は、母親や家族の姿を求めて 焼け野原の中を歩き回ったそうです。その高校生の彼も震災で両親を亡くし、 今は親戚の家に身を寄せているそうです。彼もまた両親の姿を一生懸命探し歩いたそうです。 その心労からか、彼の髪には高校生とは思えないくらい白いものが混じっていました。 戦争ではない平和なこの世の中で、時を超えて同じ思いをしている方の姿に、 私たちが想像できないくらいの大きな思いに飲み込まれ、悲しみの中にあったのではないかと思いました。 そんな中で、私たちに出来ることはなんでしょうか。答えはそれぞれ人によって異なるものなのでしょうし、 応援の仕方も違って良いと思います。自分の出来るところからの一歩を踏み出していきたいと思いました。 ひろばでお子さんと遊んでいると、4時近くに音楽が鳴り始めます。 その音楽と共にお家の方が「ほら、お片づけだよ。」と、お子さんと一緒にひろばのあちらこちらに落ちている おもちゃを片づけてくれます。お家の方が「これは、どこだっけ」と言うと子どもたちが「知ってるよ。」 とばかりに率先して片づけてくれます。片づけましょうと言ったわけではないのですが、 皆さんが片づけてくれるので、ひろばはあっという間に片づきます。初めてひろばに来た時に、 このお家の方の片づけの手際良さに驚かされました。それは、最後の片づけだけではなく、 日中でも「小さい子が踏むといけないので・・・。」と、職員の気づかないところをフォローするように 片づけてくれます。ゆりかごが皆さんの心遣いの中にあることを覚え、本当に嬉しくなりました。 ありがとうございます。 芹澤 政子 |
| ひろばに来て4ヶ月が過ぎようとしています。その間、今まで以上にお母さんやお父さんのお話を 聞く機会が沢山ありました。 お父さんもお母さんも、子どもが生まれて初めて親になるわけで、子どもたちがなぜ泣いて、 なぜぐずるのか、それに対してどう関わっていいのか分からないことだらけです。 「親だから、母になったから出来るでしょう。」「女の人には母性があるから・・。」 と言われても親になって1年目で、子どもと一緒にお父さんになり、お母さんになっていくのです。 そこから子どもと一緒に育っていくのです。 お父さんもお母さんも、子どもが生まれてからの事を多少考えてはいても、 実際一緒に生活をしていると思いがけないことが沢山あります。朝から翌朝の24時間授乳・ オムツ替えと寝る間を惜しんでの世話で、日中も育児・家事は続きます。 今までは自分と夫・家族の事 だけをすれば良かったのですが、24時間誰かの世話をし、 ここまで密に関わる経験は なかったのではないでしょうか。 生まれて嬉しいことも日を重ねるごとに「忍耐」と「試練」になることもあります。 育メンと言われるようになり、かなりお父さんたちが育児に関心を示してくれるようになりましたが、 それでも 残業・残業のお父さんにしてみれば、家にいるときだけでものんびりさせてくれと 訴えている様で、お父さんを休ませてあげる為に「ひろば」で遊んでいくお母さんもいらっしゃいます。 また、「土曜日だけでも自分が・・・。」とお父さんと一緒の子どもたちの姿を見かけるようになりました。 そんなある日、ひろばで1冊の本を見つけました。 汐見稔幸・田中千恵子・土谷みち子著の「父子手帳」です。(大月書店発行) 「お父さんになったあなたへ」と副題がついていて、『子どもとどう関わったらいいかわからない。』 『育児をやりたいけれど今の会社じゃなかなかできない。』と、板挟みのお父さんもいらっしゃるようです。 そんな時の子どもへの関わり方や奥さんを支えるひと言。一緒に出来る提案をしてくれています。 ご夫婦で読んで話題を広げたり、子育てを共通の事として考えていければいいですね。 お父さんお母さんだけでなく、子育ては一人一人違うので、ベテランと言われている お父さんやお母さん・おじいちゃん・おばあちゃんも読み返しながら、子育てを考えてみるきっかけに なさってはいかがでしょうか。 ひろばで貸し出しを行なっていますのでどうぞ手に取ってみてください。 芹澤 政子 |
| ありがとう 今までも これからも みや れいこ 著 学研ステイフル 今 私があるのは それは…。 あなたがたくさんのやさしさをくれたから 困難な時も 支えてくれたから 不安で先が見えない時 明かりをともしてくれたから あきらめずに 笑って前へすすめることを教えてくれたから さみしい時も かなしい時も 一緒にいてくれたから だから 今までのように甘えなくても しっかり立てるようになったよ そして、大切なあなたの存在に 改めて気が付いたよ もし、顔をくもらせることがあったら 私を思い出して…。 あなたがしてくれたように 私のココロをあなたに送るよ たとえ そばにいなくても 気持ちはつながっているから…。 いつもは、なかなか言えないけれど 心から ありがとう。 友人が送ってくれた小さな小さな本です。読んでいるうちに心が温かくなってきました。 東日本大地震では、多くの方が被災し、今なお困難な生活を強いられています。今まで普通に していた事がいっぺんに消えてしまうのですから、想像を絶するものがあります。募金をして も物資を送っても、本当に支援になっているのだろうか。と、思い悩んでいた時にこの詩と 93歳のおばあちゃんの笑顔に出会い(TVのニュース)ました。「困難な時・不安な時に沢 山の支えがあり、笑顔があって今を生きていける。」と語っていました。被災地の方の苦しく ても明るく生きて行こうとする姿にかえって私たちが勇気をもらっていると感じました。 ささやかな支援でも、受け取る方に「一緒にいるよ。」というメッセージが、少しでも伝われ ばと思いました。 挨拶が遅くなりましたが、4月1日より異動してきました芹澤 政子です。 今までは保育園にいましたので、家庭支援センターは全く初めてです。一からのスタートで わからない事ばかりですが、暖かいスタッフに恵まれ一つ一つ教えてもらっています。 気付かない事も沢山あると思いますので、気軽に声をかけて頂けると嬉しいです。 また 計画停電では、いくつかの事業が中止になりましたし、節電・暖房の自粛と協力をいた だきご不便をおかけしております。引き続き節電等のご協力をお願いいたします。 芹澤 政子 |
2011.1.25 発行 No.29より
| 「子どもの力を信じる」ことは難しいです。そうしたいと思っているのに、そうなっていなかったりして。 「子どもの力を信じる」ってどういうことなんでしょう。待つ、見守る、応援する、余計なことをしない、その子に必要なことと自分が必要としていることを区別する(子どものためと言いつつ、自分のためだったりします)、その子のあり方・やり方を尊重する、人格を否定しない等々思いを巡らせてみるとそんなことばが浮かんできます。 子どもの力を信じるということは、子どもの「才能を信じて」それを「伸ばしてあげる」ために「親子で何かに励む」こととは、私のイメージは違います。その子がその子のやり方で希望を持ち可能性だけでなく限界も受け入れながら『自分が』生きていく。そのことを周囲の大人が応援していくという感じでしょうか。 個性ということばは便利に使われるようになりました。個性を伸ばすということは、子どもの側からいうと、まずはその子のありようが尊重される、否定されないということだと思うのですが大人の側からすると個性ということばを、ある時は大人が満足を得るために、またある時は、大人が傷つかないようにするため、自分を守るためのものとして、都合よく使っているような気がします。(だから個性、個性と言われる中で個性を消して生きようとする子どもの現実があるのかな)本当は個性を伸ばすというより、個性はその子のあり様を尊重されることで伸びていくもので、個性があるとかないとかいうものではなく、ひとりひとりにもれなくあるもの、そして、それはその子の力を信じることとつながっているのではないでしょうか。 「この子はなんでこれができないんでしょう」「○○ちゃんはこうなのに、なんでうちの子はこうなんでしょう」あれができない、これをしない…。このことは言いかえると「私はこうしたいのにこうならない」という訴えです。いろいろな理由はくっつくけれど、要は自分の思う通りにならないことへの嘆きやいらだち。「子どもの力を信じる」ということは大人がこの欲求と折り合いをつけていくことです。今の時代、子どもの力を信じて待つことは不安との戦いかもしれませんね。他の人が耐えきれず色々なことをしてしまっているのを見聞きし、先が見えない中で我が子がその子の力でひとつひとつ葛藤しながら成長、発達していくのを見守っていく、しかもその子のスピード、その子のやり方で。競争して勝つことが大事にされる世の中で。 正しいとか正しくないとか、効率がいいとかよくないとか、そういうことをとりあえず脇に置いておいて「あなたにはあなたのやり方があったんだね」「なるほどそんな風に感じたんだ」なんて言ってもらえたら、嬉しいんじゃないかなぁ。親だってそう言ってくれる人がいたら嬉しくないですかね。そういえば世の中、お父さん、お母さんに対してそんなふうに言えてないですね。信じてもらえた人は信じられる人になる。自分のいる場所で小さな一歩から始めることにしましょう。全てにおいて正しい親はいないし、正しくあろうとする親よりもたぶん失敗しても失敗しても泣きながらでも自分をふり返り、成長していく親でこそ子どもを信じていけるようになるのでしょう。(本当は「子ども」に行きつく前に「子ども」を「自分」に置き換えることが必要なんでしょうけどネ。つまり「自分の力を信じる」です。これがまた難しい!) (宮澤) |
2010.10.25.発行 No28より
子育てって答えがないし、先も見えない。人を育てるなんていう経験もない。やり方だって人それぞれでいい。なのにみんなやっているからやれるのがあたり前と思われがち。しかも何でも母親の責任っていうプレッシャーを受け、それぞれのやり方で子育てしてきたはずの世の中の人たちが流すあたかもこれが正解、これが教科書的な情報の中を泳ぐようにして我が子と向き合う、今のお母さんたちの大変さをしみじみ思います。 なんだか世の中から、ピリピリ、イライラした空気を感じます。周囲に気を遣うことに神経をすり減らし、誰かに負けないよう、自分だけ損をしないようにアンテナを立て、そのアンテナ同士がぶつかって時には傷ついたりもして、そんな風に人との関係に安心感がもちにくい状況の中での子育ては疲れることでしょう。 知らず知らずに親ががんばっていれば、知らず知らずにがんばりを子どもにも強要したくなります。「私だってがんばっているんだから、あなたもがんばりなさいよ」そんな叱咤激励の声が聞こえてくるような気がします。「こんなにもがんばっているのに、なんで足をひっぱるのよ」という腹立ちまぎれの声も聞こえます。『いいお母さん』『立派なお母さん』になれるようがんばっているのですよね。さぼっちゃいけない、気を抜いちゃいけない、あれもこれもお母さんならやってあげなくちゃいけない、だって他の人はやれている、必死なのに楽しめとも言われる。どうすればいいの!叱らずにほめてあげなくちゃ、叱ってばかりの私はダメなお母さん。お母さんも子どももいつもニコニコ楽しそうにしている、そんな生活をイメージさせられていたかもしれませんね。今までは自分が努力すれば周囲が楽しそうにしていてくれたのかもしれません。その努力によって自分という存在を認めてもらっていたのかもしれません。でも子どもはそうはいきません、子どもの事情で生の感情をぶつけてきます。そんな経験、初めてだったら戸惑うに決まってます。自分の努力に関わらず相手は泣いたりグズグズしたりします。自身もなくなるでしょう、途方にくれてしまうかもしれません。がんばればがんばるほど。 苦しくなるからがんばらなくていいよと私は言えなくなりました。そんなに、ことは簡単ではないから。がんばっている、ホントは苦しいと思っているのに、そのことにさえ気づかないまま必死に生きている人に心から労いのことばをかけたい、今はそんな風に思っています。「きょうもよくやったね」 がんばろう、がんばりたい、がんばらねばならない、がんばるべきだ、がんばってあたり前、私はがんばってなんかいない。自分の気持ちに近いのはどれでしょう。がんばることを否定するわけではありません。ただ、今の自分の気持ちを受け入れたり、客観視することが子どもとのかかわりでは必要な気がします。 (宮澤) |
2010.7.25.発行 No27より
「仲よくしなさい」の第2弾を書くことにしました。 2歳の女の子Aちゃんと男の子Bくんのお話です。 Aちゃんはとっても繊細な女の子、その繊細さ故に先制攻撃をしてしまうところがあり、 噛みつく、ひっかく等けっこう激しい表現になってしまうけれど、すごくかわいい子です。 Bくんはおっとりした静かな子で、相手に強く出られるとひっこんでしまいがちな子。 でも、やる時はやるんだぞという信頼のおける子です。 ある日、とび箱の上からとび降りるという遊びをしている時に、大人が「わぁすごいAちゃん、 お兄ちゃんみたい(お姉ちゃんよりお兄ちゃんの方がお気に入り表現でした)」とほめると、 Aちゃん大満足。その後、挑戦したBくんにも「Bくんもお兄ちゃんだぁ」と声をかけると「Bくん、 お兄ちゃん」と嬉しそうなBくん。ところが、それを聞いていたAちゃんが「ダメ!Aちゃんが お兄ちゃん。Bくんはお兄ちゃんじゃない」と怒ったのです。「お兄ちゃんとお兄ちゃんでおんな じだよ」「じゃあ、Aちゃんはおっきいお兄ちゃんで、Bくんはちゅうくらいのお兄ちゃん」等と 必死にとりなしても「ダメ、Aちゃんがお兄ちゃんなの」と譲りません。その間に嬉しそうだった Bくんの顔は見る間にションボリしてしまい、大人も意気消沈で、Bくんに小さい声で「Bくん だってお兄ちゃんになりたいよね。だって上手にできたもんね」と言うのが精一杯。Bくんに 対して申し訳ない気持ちがして、なんだか情けなくなってしまいました。そんなこんなの3日後、 一緒に食事をしていた時になんと突然Aちゃんが「Bくんもお兄ちゃんだもんね」と大人に 言ったのです。それを聞いていたBくんが「Aちゃんが、Bくんもお兄ちゃんだって」。「よかった ねえ、Bくんもお兄ちゃんだって。AちゃんもBくんもおんなじお兄ちゃんだね」の大人のことばに 2人はニッコリして「ウン」「おんなじだねえ」。この子どもたち2人に救われた大人は私です。 この時の光景は今もはっきり覚えています。感動して、それこそ涙でウルッとなったくらいに。 あの時の「お兄ちゃん」は自分のもの、取らないでとばかりに主張していたAちゃんの必死な 気持ち、Bくんの「ボクだって」という悲しい気持ち、そして「お兄ちゃん」を2人で分かちあって くれた瞬間。3日間、それぞれの気持ちの中で葛藤していたものが出口を見つけて、それぞれ の心に届きました。子どもってすごいですよね。3日の間、Aちゃんの心の中はどんな風に 変化したのかなと思います。1人で持っていたものを友だちと共有するのも悪くないかなと 思ったのでしょうか。 大切なことは、子どもにも小さいながらに自分の気持ちを成長させていく力があるんだと いうことを大人が信じること、そして成長していく時間を保障する、心が動いていく過程を見守 っているということなのだと思います。時間が必要なのです。(でも大人より子どもの方が時間 がかからないかもしれませんがね)仲よくするって自分の感情を抑えることや人に合わせるこ とではなく、一緒に何かをすることで得られる感情を味わうってことなのかもしれませんね。 ちなみに、「お兄ちゃん」ということばがAちゃんにとって大事なことばだということに私が思いを はせていれば、展開は違ったのかもしれません。でも、頭ごなしにAちゃんを叱らなかったこと だけで「まる。私にしてはよくやったよ」となぐさめることにしましょう。 (宮澤) |
2010.4.30.発行 No26より
| 「友だち」 「仲よく」 小さい頃から繰り返し耳にした言葉です。 私は、この「仲よく」という言葉に現実味のない、それでいて強要されるようなそんな雰囲気を 小さい時から感じていたような気がします。大人に言われるとウソっぽい感じがしていたので しょうね。ちょっとおへそが曲がってついていた子だったのかもしれませんが。 なぜ、こんなことを唐突に書き始めたかというと「仲よくしなさい」という言葉を聞く機会が増 え、少しばかり小さい頃の気持ちを思い出したのです。お友だちが好き、一緒にいると楽しい と思えるのは自然に湧きあがってくる感情であって、好きになりなさい、楽しいと思いなさいと は強要も説得もできないものですね。「仲よくしなさい」からは、そんな子どもの心に立ち入り 過ぎている、押しつけてはいけないことを押しつけているような響きを感じ取ってしまうのです。 仲よしって、小さい子どもたちの場合流動的なもので「仲よくできない子はダメな子」という 程 、大層なことでもないんだけどなあと思ってしまいます。大人だって誰とでも仲よくなれる わけではないし、表面ニコニコしていても好きな相手もいれば苦手な相手もいて、適度に相 手に合わせて距離をとって生きてます。子どもだって同じです。自分の領域にズカズカと入っ てこられると抵抗があります。相手に近づいてこられるだけでいやな子もいれば、自分のもの に触れられる、取られると攻撃してしまう子もいます。自分が手にしているものは絶対渡さな いぞとがんばる子がいれば、領域に入られるくらいなら渡しちゃえという子もいます。大人だ って、体は大きくなっていても突き詰めれば(手に持ってるものがおもちゃや食べものじゃなく てもっと複雑になるけれど)子どもたちのすることをちょっと高度にしたような感じで相手に合 わせ、または自分に合わせたやり方で関係性のやり繰りをしてます。子どもにもその子なり のやり方があります。大切なのは、自分なりのやり方を駆使しながらじぶんの領域(自分の持 っているものや場所、要求、思い等)を守ろうといている、そのがんばる姿を大人にそのやり 方はダメと否定されることなく、それぞれの子どもたちが尊重されるその積み重ねの中で相 手を受け入れていく、そのプロセスなのかなと思います。 ケンカと共感は正しくないことと正しいことに分けられるものではなく、両方共とても近い、親 しい間柄です。そこをいったり、きたりして成長していきます。一直線ではなくジグザグに。 ジグザグを見守っていくこと ― あっちに目をやり、こっちに目をやりとしていくことで大人の 子どもを見る目に巾がでてくるのかもしれませんね。 大人自身も迷ったり、悩んだりジグザグして人としての巾ができるから、そのプロセスもまた よしとしましょうか。 (宮澤) 子ども同士のトラブルが起こったら、例えば… 1.大人があまり大騒ぎせず 2.知っている人同士であぶなくないなら、時には少し見守っていてもOK 3.子どもの気持ちを代弁してあげる 「貸して欲しかったんだね」 「一緒にやりたかったんだね」 4.相手の子のつもりも代弁してあげる 「まだ遊びたいんだって」 「楽しそうだなって見てるんだって」 (相手の子が攻撃者じゃないことを伝える感じで) 5.手を出してしまったら、出されてしまったら 「お友だち痛いよ、貸してだよね」 「痛かったね、お友だちにもうやらないでってお話しようね」 6.お友だちのもっているものが欲しかったら 「あとで貸してね」 「終わったら貸してね」 と相手に伝える 持っている本人だったら 「あとで貸してあげようか」 「終わったら貸してあげようか」 7.どうしてもあきらめられなかったら他のことで気をそらすか、それでもダメなら泣かせて あげて、泣きやめたらほめてあげる 8.ムリやり貸してあげなさいと迫らない、または勝手に貸してあげてしまわない 「いっぱい持っているから1つでいいでしょ」 は、大人の都合で 「1つ貸してあげる?」 はOKだけれど(子どもに正当な拒否権あり) 「1つ貸してあげなさい」(拒否権なし) はどうかな いっぱい集めたい時期もあるので、強要し続けるとかえって執着が長引きます (この方法が通用すればいい子で、通用しないと悪い子ということはありませんので念のため) |
| 「待つ」ことって「静」のように見えて、すごくエネルギーを使う行為のような気がします。 「待っているという行為のの裏で、心の中では、モゾモゾと動いている感情があるのではないでしょうか。 単純に人や物が来るのを待っているだけでも、来る、来ないを巡って期待(いやなものの時には恐れ) があるのでドキドキしたり、ワクワクしたり、ドンヨリしたり。時間や状況の経過の中で気持が変わっていく のではないかと思います。その気持の変化には、自分のそれまでの経験も影響しますしねぇ。 「今度はダメかも」「今度もダメかも」「今度はダメかも」「今度も大丈夫」「今度は大丈夫」、「期待は裏切 らない」「裏切られるに決まっている」、「期待通りにいかなかったら大変なことになる」「ならなかったらまた 考えよう」。随分単純化してしまいましたが、こんなことがあった、あんなことばかりだった、○○してみたい のに○○にならなかった等々、様々な経験の蓄積が待っている」時の気持に影響を与えます。 複雑な絡みの中で「今」「ここで」何かを「待つ」自分がいることになるでしょう。 その「何か」が子どもの成長だったらどうでしょう。子どもを育てる、子どもが育つというのは、「待つ」こと が多く、またそのことが大切なような気がします。(とこんなことを書いている私は、待つことが、超とかドと かがつくぐらい下手ですが。)言い訳がましいですが、人の成長を待つって難しいことです。 手を出したり、口を出したりすることの方が楽ですし、ついやりたくなるんですよね。しかも、全く世話がや けるとかブツブツ言っちゃたりして、 かつて、仕事で仕事で自分が子どもに関わっている場面をビデオに撮って見た時にいらない言葉を何 と沢山発していることか、又肝心なとこrを見ていないか(ということは、肝心なところで言葉をかけていない ということです。)ということにショックを受けたことがあります。いらない言葉というのは、私がその子を待て ずに、子どもにかけている振りをして、自分にかけている、または誰かを意識しての言葉でした。 自分の安心のために、言い訳のために。全部を捨ててしまうことは無理だけど、せめてこんな私である自覚 は大事と自分で自分を慰めつつ、子どもが自ら育っていくことを信じ、見守り続けていくことが難しいことかと 実感。しょげますよねぇ。待つことには葛藤があります。不安になりますから。自分の心の中の感情を子ども にう放り投げず、に自分で抱えていかないとなりませんからしんどいです。それに外から甘いだの、何も しなくていいのかだの、遅れるだのなんだかんだ言われそうですしね。 待つ=何もしないということではありません。子どもの成長を待つことは、相手を信じる気持があり、心を 向けています。見たくない姿にもじっと目をそらさずにいます。お互いの心の揺れからも。子ども達は、本当 に待っているとその子の力で育っていきます。もし誰かが自分をいつまでも信じ待っていてくれたら安心でき ませんか。大人だってそういう感覚があったら支えになりますよね。きっと。 ('09.1.28) |
2009.10.24.発行 No.24より
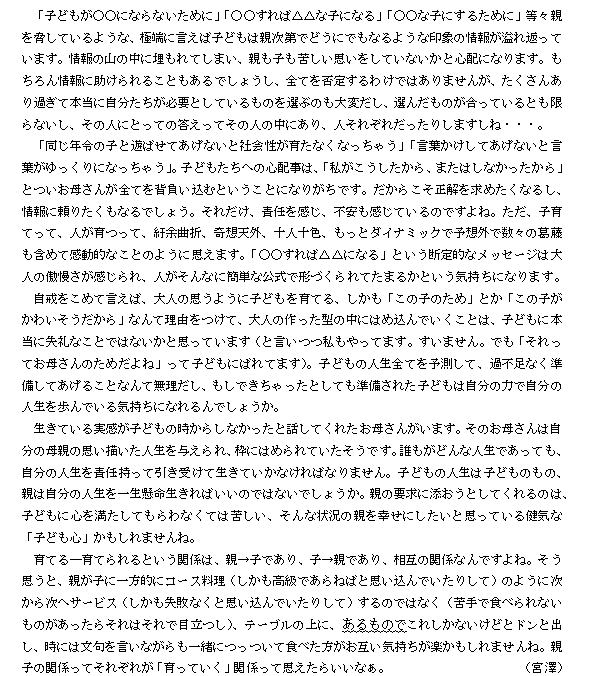
2009.07.25発行 №23より
思い通りになることとならないこと、こうしたいという気持ちとそうはならない(できない)という現実 、そういう狭間で人間って成長していくんだなあとしみじみと思いつつ、わかっちゃいるけどしんど かったり、傷ついたりすることが多々あります。 子育ては、思い通りにならないことの連続です。振り回されて、腹が立ったり、疲れたり。「全て思 い通りにいってるわ」と思っている人がいたら「もしかしたら誰かが遠慮してくれてないですか」な んてつぶやいてみたくもなります。 思い通りにしたい、してほしい気持ちは、誰にでもあることでしょう。子どもは、そんな気持ちの固 まりのような存在です。全身で自分の思いを通そうとします。親が、どんな状況でもお腹が空けば 泣き、気分が悪くなればぐずります。「子どもはいいなあ、大人はそうはいかないんだよ」と思った 事はありませんか。「こっちの大変さもわかってよ。がまんしなさい。」とイライラすることもあるで しょう。溜まった大変さや不安はついどこかにぶつけたくなるものです。親も怒りながら「わかって よー」とどこかで叫んでいるのですよね。わかってほしい相手にわかってもらえない時(つまり自 分の思い通りに受けとめてもらえない時)本当は、大人に受けとめてもらう側であるはずの子ども に大人の気持ちや大変さの受け手をさせてしまうことが結構あります。大人が子どもで大人とい うことです。 大人が子どもを守っているつもりになっていても、子どもが大人を守っているということもあります よね。気まずい人間関係の中で子どもの存在が空気をなごませてくれたり、お母さんの代わりに お父さんを叱ってくれたり(逆もあり)、お母さんが緊張するところは、子どもが大泣きしてその気 持ちを代弁したり、早くその場を離れられるようにしてくれたり、言いにくいことをズバッと言ってく れちゃったり。小さい頃本当は、面白くないのに無理して笑ったことありませんか?子どもって誰 かの為に大人が気づかない努力をしていることが沢山あるんです。自分の要求だけで生きてい るように見えますけどね。なかなか奥の深い面々なのです。自分の思い通りにしたい固まりとさっ き書きましたがどちらの側面も持っているということですかね。親子って面白いですね、思い通り にしようとお互い張り合ったり、反発し合ったり、そうかと思うとどこかで守り合ったり許し合ったり。 黒も白もドロドロとまざりあっているところがあります。 助け合いつつも親と一体化するのではなく、自分は親とは違う人間だと主張できる子がいい子な んじゃないですかね。 そう考えると早い段階で我が子のことを、「相手が思い通りにいかない別の人間だ」と痛感できる 出来事に出合うことは、親にとって案外幸せなことかもしれませんね。相手をコントロールしようと することは、とてもエネルギーを使うし、大概は、相手をコントロールできないし、できたとしても どちらの結果もむなしいものですから。 (宮澤) |
2009.5.2.発行 No22より
| いいお母さんってどんなお母さんなんでしょうね。みなさんは、「いいお母さん」という言葉にど んなイメージを持っていらっしゃるのでしょう。そして、今の自分をどんなお母さんと受けとめて いらっしゃるのでしょうね。 理想と現実、ギャップがあるのは当たり前とは思いつつ、現実の自分をまっすぐ見るのは、 けっこう難易度が高いことです。理想とまではいかなくてもあんな風だったらいいなぁ、あんな風 になりたいと思っていたり、それほど意識していなくてもこうでなくちゃ、こうであるべきなんてこと が頭の片隅にあったりしますよね。私の中にも願望・欲望・執着・空想・妄想等と各種取り混ぜ て「こうありたい自分」「こうあらねばならない自分」がうず巻いています。また、稀に「あるがまま でいいか」と思える部分もあります。どうでもいいことと、どうでもよくないこと、どういうことがどう でもよくて、どういうことがどうでもよくないのか、人それぞれですよね。だからこそそこに私の個 性、特徴があるんだなとつくづく思います。 どうでもいいと思っていることを誰かにこだわられると面倒くさいと思ったり、どうでもよくないと 思っていることをスルーされたり、ぞんざいに扱われたりするとわかってもらいたかったのにー、 となりませんか。相手にも私と同じようにどうでもいいこととよくないことの個性があり、特徴があ るのに自分の持っているものを押しつけたくなるんですよね、これがまた。どうしても譲れないこ と、譲りたくないことがあったら、そこにこそ自分自身のことがよく見えるポイントがあるのかもし れません。だから、こんなことでこだわるなんて大人気ないとか、こだわらない相手が悪いとか、 自分や相手を黙らせてしまうのではなく、このことは私にとっては大事なことなんだと認めてあげ たらどうでしょう。自分に課していることは、何でしょう。子どもに対して課してしまうことはなんで しょう。 常識・マナー・損得とか世間の尺度とか、人間が生きていく中でどうしても脳裏にチラついてしま うことではありますが、「それってホント?」「それって何のため?」「誰のため?」「私はそうした い?」って時には問いかけてみませんか? 「いい」とか「悪い」とかいったい誰にとって「いい」「悪い」なのかなぁって。 「いいお母さん」「いい子」と「悪い(ダメな)お母さん」、「悪い(ダメ)子」、たいていはその間をチョ ロチョロして生きているんじゃないでしょうか。決して固定されたものではなく、しかもその「いい 悪い」にも調子が…機嫌が…手際が…という地域限定だったり、「今は」という期間限定だった り、得意不得意だったり、個性だったり、習慣だったり、中身も色々です。いい・悪いの部屋に 全て分けて、閉じ込めてしまわずに、中身をよく見てバラしておくことをお勧めしたいと思います。 それともう一つ、もし今の自分の人格を否定するような理想が存在したらろくな奴じゃないかも しれませんよ。老婆心ながら。だって、そんな権利誰にもないですから。 こんなお母さんじゃダメなんじゃないかと思ったら、そんな風に思いながらも一生懸命子どもを 育てている、目には見えないけれど確実に存在する仲間達を思い浮かべてください。あなたは ひとりではありませんよ。 (宮澤) |
| 「自我」という言葉を聞いたことがありますか。自我は「自分で考え、自分で決める」主体 であり、固有である自分の価値を自分に教える等自分というものに気づき、自分自身との関 係や人との関係を自分を尊重しつつ、よりよくなるよう調整していく役割をもつものだそうです 。なかなかに奥が深そうでしょう。1才半頃の「イヤ」という反発が自我の誕生を知らせてくれ ます。 そんな喜ぶべき自我の誕生のお年頃だというのに、子どもたちが「イヤ」「自分で」「○○し たいの」等々と叫び出すと親の方も威信をかけて、つい立ち向かおうとしてしまいます。「もう 時間がないでしょう」「トイレ行かないとオムツがはずれないでしょ」「いつも言うことをきいてい たらわがままな子になっちゃうかも」「躾のできない親っていわれそう」「あー、またこれ片づけ るの私じゃない」etc.頭の中を色々な思いがグルグルします。そんなことを知ってか知らずか、 こちらがあせればあせる程悪循環。で、こじれにこじれて子どもは大泣き、親は怒りが納まら ずなんてことは日常茶飯事。外でやられたら子ども共々隠れてしまいたくもなりますよね。顔 は余裕のある振りをしながら、子どもを引っ張る手にめいっぱい力が入ってるなんてことも大 いにあり。 ある時は他の人の親子バトルを見て、私だけじゃなかったって秘かに胸をなでおろし、また ある時は、見られている立場となり、うまくこの場を収めなくっちゃと自分で自分にいらぬプレ ッシャーかけちゃって抜き差しならない事態になったりして。 客観的に見ると「親心」とやらは、一生懸命で時には滑稽なものです。 よくも悪くも子どもに関わる時に顔を出す親心(大人目線の解釈:子どもが幸せになります ようにという思い、子ども目線の解釈:大人の都合に合わせたコントロール)を見事に踏みつ ぶしてくれるのが子どもの発達です。「自分」を作り上げていく営みは、なかなかに芸術的であ り、壮絶だなぁと思います。親のすることを「イヤ」「ダメ」「キライ」「自分で」「しないで」と体当 たりで否定してくる2歳代。途中こぜり合いを繰り返しながら、思春期でまた自分の存在をか けて立ち向かってきます。こうまでしないと「自分」をつくっていかれないのか。親にとっても子 にとっても生みの苦しみですね。 思えば出産で体は別々になっても母子が一体化してしか育ち得なかった命がお母さんから離 れることの不安を抱えつつ、必死の思いで「自分」(1人の人間としての尊厳)を作り上げてい く。その時期の子どもの姿は、そうまでして親の愛情を確かめずにはいられないのか、そうま でしないと親と別の人格としてはばたいていけないのかとちょっとジ〜ンとくるものがあります。 いいとか悪いとか、躾とかをちょっと横に置いて、たまにこんな風に子どもの自己主張をなが めてみると景色が違って見えるかもしれませんね。 その子によって自己主張の激しさは様々です。あまり出さない子、これでもかと出す子、どち らがいいということではなく、その子らしさとしてどう関わるかを考えてあげたいと思います。そ の子らしい出し方にどう付き合うか、なかなかの難題ですので、1人1人のお話やご自身の自 我の育ちについては、ひろばでかお電話ですることにしませんか。 (宮澤) |
たくさんのA子さんへ 「子どもが生まれてから、お母さん友達をつくらなくちゃととにかくあせりました。」とあなたは言っていましたね。でも無理に他の人に合わせていたら疲れてしまったとか、気をつかっているうちはいいけれど本音で突っ込んだ話をしたら相手がひいてしまったり、逆にこんなことを言ったらひいてしまうのではと、余計に気を使って自分のほうから離れてしまったり、色々なことがありましたね。そして周りのみんなは、うまくやっているのに「私だけうまく友達がつくれない」「私がおかしいんじゃないか」って自己嫌悪におちいってイライラして。自分には合わない、なんだか自分は無理してるって感じていても輪から抜けられない、「私は私」って思える人がうらやましいなんて話もしていましたっけ。コミュニケーションって難しいですね。自分の思い通りにならない「相手」がいることだからです。相手に求めることがお互いに違っていたりまた求め過ぎていたり、それからあげたつもり、もらったつもりの気持ちや言葉がずれていたり、タイミングもあるでしょうし。あらっ、こんなこと言っているともっと人との関係が面倒になってしまいますか。 私が言いたかったのは、相手のあることなので「自分がダメなんだ」というところに着地しないでねということなんです。そして「自分だけがこうなんだ」と思わないでください。同じ悩みを抱えている人は沢山いるんですよということです。 心の距離のとり方は、ひとりひとりが決めることですから。「無理しなさんな」あなたは充分魅力的でステキな人です。人の中にいられることと同じようにひとりでいられることも大事なことだと思います。どうしても同じ年齢の子がいるお母さん同士で同じくらいの年齢、考え方が似ている等、同質の集団を求めがちですが、そうじゃなくても自分が楽だったり安心できたりする場を選んでいいのだと思います。ひとりひとり誰とつながるか、どんな風につながるか、それこそ個性というもの。 まず自分の心の声を聴いてあげてくださいね。「友達のいない人って思われたくないんだな」「不安だから同じように悩んでる人に共感してほしいんだなぁ」とか「子どもにも友達をつくってあげなくちゃとあせってるんだなぁ」とか。今、自分が何を考え、どういう関係をもちたいと思っているのか感じてみてください。そして「わかった。大丈夫だよ。」と声をかけてあげてくださいね。 子ども達だってまず自分の感情を理解し、自尊心を高め、自分とは違う他人が存在するんだとわかってから、他人の気持ちがわかるようになり、仲間づくりが始まるのですから。子どもも大人も自尊心を大切にしながら、自分を責めることなくあせらずゆっくり、次の出会いの時を待ちましょう。そして、自分たちのテンポで安心できる関係を築いてくださいね。 (安心できるお相手って、人に限らず風・木・大地・本・音楽・etc.その人の感覚で色々ありです。) (宮澤) |
2008.8.1.発行 No.19より
|
親だって、多くの親が我が子に自分を否定するように育ってほしいなんて思っていないのに、何故難しいんでしょう。こんなことがすぐわかって、すぐにできるようになるなら世の中変わっているかもしれません。以前、「前に進めと言われて進もうとすると進めない。ふとうしろを見るとその人にスカートの裾を踏まれていた」というような内容のことをおっしゃた政治家の方がいました。覚えているでしょうか。世間にはありがちなことです。でも私にも心当たりがあります。「前向きに」とか「積極的に」とか、「失敗を恐れず」なんて格好のいいことを言いつつ、いざ子どもが動こうとしたり、考え始めた時に「よく考えたの」「それは無理なんじゃないか」「こっちの方が得なんじゃない」と引止めにかかる。子どもにしたら「いったいどっちなんだ」という感じですよね。こんなこともあります。子どもができたことを、またはうまくいかなかったことを「お母さんもできた」「お母さんはできた」なんて張り合っていたり、トホホ・・・です。親が子どもの人生に入り込んでああしろ、こうしろと采配をふるうのではなく一歩下がって応援すること、それができたらどんなに子どもは嬉しいでしょう。子どもは(大人もだなぁ)「そうそう、それでOK」「大丈夫、もう一回やってごらん」そういうまなざしを待っているのですよね。私たちの心の中には自分の今の現実を冷静に見ている人と自分にダメ出しをする人と自分にOKサインを送ってくれる人がいるような気がします。バランスが大事なのでしょうね。でも各々癖というか習い性があって、ダメ出しをする人が独裁者のように強いタイプもあります。またそういう時期もあります。独裁者はどんな姿をしていますか、誰かに似てるでしょうか。口調はどうでしょう。その人の言うことは本当に絶対正しいのでしょうか。ダメ出し人間が強ければ数で勝負です。応援してくれる人を勝手に増やしましょう。私は時々、ハチマキをして、旗を持って私を応援してくれる応援団を思い描きます。顔のわかる人もいればわからない人もいます。そんなことでもちょっと安心できます。きっと人それぞれ応援団のつくり方が違うとは思いますが。 子どもたちには、その子の中にたくさんの応援の言葉を残してあげたいと切に願います。小さい頃だったら「わかった。そうだよね」「〜したかったんだ」「〜って思ったんだね」「もう1回やってみようか」「大丈夫。見てるよ」「がんばったね」etc. 応援団は誰でもなれるんです。親だけがなるものではなく(もちろん親がなってくれることが子どもが一番嬉しいことですよ)大人がみんななれればいいのです。そうしたら子どもたちは極限で踏んばれる、自分を守り、救える人に、そして他の人の痛みがわかる人になれると思うんですよね。子どもだけ応援してもらえてずるい、私のことも応援して!という気持ちももちろんOKです。 (おまけのひとり言...子どもには、正しい親ではなく弱さを抱える親と思ってもらえたらいいな。等身大の人間として理解し合えた方がお互い苦しくなさそうだから。「そんな親でも大丈夫」と自分を慰める日々です。) |
2008.5.1.発行 No.18より
|
子育てをしていて、私は「子どもに許されながら親をやっているな」と思うことがよくあります。つい、親の方が子どもを許したり、待っていたり、「あげている」気になっているのですが、よくよく考えてみると子どもも親を許し、その成長を待っていてくれているんだとドキッとするのです。子どもが小さい時にはそのことに気づかなくても、大きくなるとこの子は、「私よりも私を知っているかも」とか「私のことをずーっとじっと見てきたんだなぁ」と、実感することがあります。(実感することを言われちゃうんです。という表現が正確かな)子どもの言動に、自分が裸にされたような恥ずかしさや、隠したい認めたくないという気持ちから、大人が逆上してしまうなんてことありますよね。子どもは鋭いから。 許す・許されるとか、我慢する・我慢してもらうとかは、誰かが片方の役割ばかりしているとバランスがとれません。また、誰かのせいで片方の役割ばかりやらされていると思うと、不満も溜まります。特に家族は、距離をとるのが難しいので苦しくなりますね。「お互い様」。親子間でもこんな風に思えたらいいですねぇ。「お互い様」には「許し合う」「感謝し合う」が入っているからホッとします。 小さい時から、許す・我慢する役割ばかりこなしていたら、どこかで誰かにその役割をとってもらいたくなりますよね。そうしないと身がもたないから。 親になると子どもにその役割をとらせたくなったりもします。もし、そうであったら自分を責めることなく、でもそういう自分を自覚してくださいね。親が自覚しているかしていないかに、子どもは敏感ですから。無自覚って相手を傷つけたり、相手に一方的に我慢を強いたりしそうなので。 今、我慢できなくなっていたり、がんばれなくなっている人はダメな人ではなく、以前どこかで、そのことを精一杯したことがある人なのだと思います。だから、今の自分を全てと思って、ダメ出しせずに、何のために何を我慢したり、がんばったり(がんばるって、体を使う行動だけでなく、心を使う・脳を使うことも入りますよ。念のため)してきたのかなぁと考えてみてください。そんな自分の業績を認めてあげることです。一人ではできなかったら、自分は誰かに手伝ってもらうに値する価値ある存在だと胸を張って、誰かに手伝ってもらいましょう。 |
2008.1.22.発行 No.17より
「泣くのは赤ちゃんの仕事だから」と言われても、泣き声を聞いていて平気とは中々なれないものです。下の子は、全然平気という方は 多いかもしれませんが、初めての子や出産時や出産後に何か心配なことがあった時、又は自分ひとりで育てているような気持ちでいる 時、そんな時の子どもの泣き声には敏感になってしまいますね、きっと。 子どもはよく泣きます。場所も時間も考えずに、羨ましくなることがあるくらいに。コミュニケーションの手段だったり、気持ちの発散だったり、賢くなると真似という技を使って大人を動かしたり、いずれにしても子どもにとっては必要なことなのでしょうね。決して泣くことで親を追いつめたり、責めたりしているわけではありません。そんなことわかっているのに、「早く泣き止ませなくては」と焦ったり、「なんで泣いているの」とこちらが泣きたくなったり、心配になったり、怒りを感じたり、また、「私がダメな母だから泣かせてしまった」と自分を責めたりと、いろいろな気持ちが 湧いてきたことはありませんか。 そんな時は、自分だけがそんな気持ちになって、他のお母さんは皆もっと『明るく』『上手に』『立派に』やれているなんて思っていたりするんですよね。(『するんですよね』って決めつけちゃっていますが、私がそうでしたし、同じ様なお母さん達の声を沢山きくものですから、つい・・・です。) あるお母さんがしてくれた話に心が動きました。子どもと二人でお店に行って、お菓子を買いました。その子は、袋にお菓子を入れて貰って、自分で持って帰ることにこだわり中でした。でも、その日はお店のおじさんが、袋ではなく、お菓子にテープを貼ってくれちゃったのです。その子は泣きました、多分思いっきり泣いたのでしょうね。お母さんはその子をひどく怒ったそうです。それは、その子が聞きわけがなかったからではなく、自分がおじさんにお菓子を袋に入れて下さいと言えなかったダメなお母さんである自分を責め、泣かれていることが辛くなってしまったのだそうです。 子どもに黙って欲しくて感情をぶつけてしまったのです。同じ場面ではなくても、似たような場面、心の動きを経験したことのある方はいるのではないでしょうか。我が子のためなら自分を犠牲にしたり、誰よりも強くあったり、賢くあったり、理想的な母であらねばならないと思っていて、そうでない自分が出てくると許せない、それが自分を責め、こどもを責めることにつながることもあれば、他者を責めることにつながったりするかもしれません。 このお母さんは、『こんなに小さい話で』と恐縮していましたが、とても大切なことがいっぱい詰まっているお話に思えました。誰でも、理想はあります。そうなりたいと思うこともステキなことです。でもね、理想と現在(いま)を比べて足りないことを探してしまう必要はないのですよ。理想と現実のギャップはあるにきまっています。そのギャップを抱えながら生きることに、時には自分を笑ったり、悲しんだり、悔しがったり、可愛く思ったり・・・・・ そんなことのできるお母さんを見て育つ子どもは、どんなに励まされることでしょう。いいお母さんより、こんな風に生きていっていいんだと伝えられるお母さんて。ケッコウかっこいいと思うんだけいどなぁ。 |
2007.10.20.発行 No.16より
| 感情の取り扱いは、本当に難しいものだと思います。自分の感情も他人の感情もです。私たちは生活している中で、ついついこれはいい、これ は悪い、これは白、これは黒等とどちらかに分けることをしがちじゃないでしょうか。どちらかに分けてしまうことで取り敢えず落ちつくというか、どちらにも入れられないことが不安というか、そんなことってないですか?行動だけではなく、自分や他人の気持ちにもついそんなことをしてしまい がちです。これは、いい感情、これは悪い感情、『こんな事を思うなんて、私はなんて嫌な人間なんだろう』『こんな風に思ってはいけない』等々 成績つけてますよね、けっこう。『子どもが可愛くない』っていう感情は、どちらのポケットにいれますか。『×』の方ですか?そのことで、自分を 責めているお母さんが沢山います。赤の他人なら、自分と遠い存在の人なら、その人のことをどう思おうが自分のことを責める気持ちは薄いので はないですか。遠い人には、こうあるべきというしばりも少ないですし、もともと関心も薄いでしょうし、関係が近いほど感情の色も濃くなります。 (もし、遠い人なのに執着してしまうとしたら、何か理由はあるのかもしれませんが)肯定の感情の色も濃いし、否定の感情も濃いでしょう。自然な ことですよね。ましてや、出産前からずっと一心同体の生活をしてきた我が子ですから。子育ては自分の子ども時代の影響を受けます。複雑でグ チャグチャになったとしても当然なことです。 我が子が可愛いと思えないと葛藤するということは、紛れもなく、一番身近において上げていればこそで、無関心なら悩みませんものね。近くに 存在を感じれば感じるほど、自分と子どもが分けられなければ余裕もなくなり、見えるものも見えなくなります。今この時期、この条件で感じること が全てのような気がして、頭の中をグルグル巡ったりしてね。 人間ですから、可愛い可愛くないが同居していたり、可愛いと思う時と、可愛くないと思う時があったり、今はこうだけど、お互いが成長する、協 力してくれる人が現れる等、条件が変わる、一生の中では、変化をしていくなど、波があり、変化があり、成長があります。 子育てでは今のこの瞬間を切り取って、これはこうに違いない、ずっとこうなのだ、将来こうなる等と思いがちです。でも瞬間、瞬間で親も子も 変化し、積み重なっているのです。その人間冥利につきる『瞬間』が見える余裕をもち、子どもの距離をもつことが大切です。よその子なら『大丈 夫』と思えることが、我が子だと思えませんね。時には、自分とは離れたそんざいとして、興味深く眺め回してみてはいかがですか。我が子に対し て、目からウロコの経験が出来るかもしれませんよ。『親子』が苦しければ、同時代を生きる『同志』だっていいじゃありませんか。可愛いとか可愛 くないとか、いい子だとかそうじゃないとかって、どうでもよかったりして。お互い相手の成長を信じられるということが大事なのかなと思います。 因みに余談ですが、感情に成績をつけることって、とっても自分に対しても、相手に対しても失礼なことなので、けっこう根にもたれるかも。 |
「どんな子に育ってほしいですか?」という質問にどんな風に答えるのでしょう。 『思いやりのある子』『優しい子』『心身ともにたくましい子』『頭のいい子』etc.お父さんとお母さんでは、イメージが違うかもしれませんね。 また、以前と今でも違うかもしれません。私も、結婚前・出産の時、その後も子どもや私の年齢と共に微妙に変わっています。 こうして、親の子どもに対する願いは、人によって、時期によって、そして親が生きてきた歴史によって違ってくるのでしょうね。でも、全て余計なものを取り払ってしまったら、「生きていて欲しい。」ここに行き着くのではないでしょうか。こんな風に思ってもらっていたら、子どもたちも安心して、大切な子ども時代を過ごせそうです。つまり『生きること』で全てOKをもらえる、自分の存在を認めてもらえるからです。子ども達は、大人たちの(特に親の)、言葉ではなく、心を聴きとって育ちます。もっと小さい頃には、大人の表情・声・身体の緊張・空気などから心を感じ取っているのでしょう。すごいことです。でもそれは、まだまだ力の弱い子ども達が生きていくのに必要なことなのだと思います。親が想像する以上に子どもは、親にその存在を認めてもらおうと頑張っています。それは、自分が子どもだった頃を思い出すと理解できるのではないでしょうか。 いい子だったらOK、○○ができたらOK、親のOKをもらう為の『条件』が何なのかに子どもは敏感です。(先取りだってできちゃういますから)それを受け入れようとする子どももいれば、抵抗する子どももいますが、どちらもちゃんと感じ取っているからこそです。親が疲れている、忙しい、余裕がない、そんなことも、みんなお見通しですよね。気を使ってくれるんです。とは言え、不安がいっぱいの時代にあって、子育てに対しての視線も厳しい中、条件つけずにおおらかに子育てをしたいと思っても大変なことでしょう。いやでも色々な情報が入ってきますから。ましてや、親の欲求なのに、自分の欲求と思い込んで努力し続けて大人になり、親になったとしたら、自分が生きていることにOKが出せないでいるとしたら、それは困難を極めることでしょう。 せめて、自分を縛っている親の『条件』を思い起こし、冒頭に書いたように、それは、その時々、人によって、時期によって変わるような決して『絶対的なもの』ではなかったということを、また我が子につけた条件は、どんなことで、どうしてそれを必要とするのかを、考えてみてはいかがでしょうか。(『いい母』『いい子』像も各々の時代、各々の人間が作り出すもので、それだけ勝手なものだってことですよ。) どんな子とも仲良くできて、好き嫌いもなく、何でも食べて、積極的でリーダーシップがあって、協調性があって、勉強が出来て、優しくて、健康で・・・なんて並べてみるとあり得なそうなこと結構望んでいたりするけれど、自分が望まれたら、ゲッソリしそうだし、何より逆でも立派に豊かに生きていけますよね。きっとそういう子に育ってほしいというより、そういう子の親になりたいってことなんでしょうね。勿論私も含めて。 |
| 「どんな子に育ってほしいですか?」という質問にどんな風に答えるのでしょう。 『思いやりのある子』『優しい子』『心身ともにたくましい子』『頭のいい子』etc.お父さんとお母さんでは、イメージが違うかもしれませんね。 また、以前と今でも違うかもしれません。私も、結婚前・出産の時、その後も子どもや私の年齢と共に微妙に変わっています。 こうして、親の子どもに対する願いは、人によって、時期によって、そして親が生きてきた歴史によって違ってくるのでしょうね。でも、全て余計なものを取り払ってしまったら、「生きていて欲しい。」ここに行き着くのではないでしょうか。こんな風に思ってもらっていたら、子どもたちも安心して、大切な子ども時代を過ごせそうです。つまり『生きること』で全てOKをもらえる、自分の存在を認めてもらえるからです。 子ども達は、大人たちの(特に親の)、言葉ではなく、心を聴きとって育ちます。もっと小さい頃には、大人の表情・声・身体の緊張・空気 などから心を感じ取っているのでしょう。すごいことです。でもそれは、まだまだ力の弱い子ども達が生きていくのに必要なことなのだと思い ます。親が想像する以上に子どもは、親にその存在を認めてもらおうと頑張っています。それは、自分が子どもだった頃を思い出すと理解できるのではないでしょうか。 いい子だったらOK、○○ができたらOK、親のOKをもらう為の『条件』が何なのかに子どもは敏感です。(先取りだってできちゃういますから)それを受け入れようとする子どももいれば、抵抗する子どももいますが、どちらもちゃんと感じ取っているからこそです。親が疲れている、忙しい、余裕がない、そんなことも、みんなお見通しですよね。気を使ってくれるんです。とは言え、不安がいっぱいの時代にあって、子育てに対しての視線も厳しい中、条件つけずにおおらかに子育てをしたいと思っても大変なことでしょう。いやでも色々な情報が入ってきますから。 ましてや、親の欲求なのに、自分の欲求と思い込んで努力し続けて大人になり、親になったとしたら、自分が生きていることにOKが出せないでいるとしたら、それは困難を極めることでしょう。 せめて、自分を縛っている親の『条件』を思い起こし、冒頭に書いたように、それは、その時々、人によって、時期によって変わるような決して『絶対的なもの』ではなかったということを、また我が子につけた条件は、どんなことで、どうしてそれを必要とするのかを、考えてみてはいかがでしょうか。(『いい母』『いい子』像も各々の時代、各々の人間が作り出すもので、それだけ勝手なものだってことですよ。) どんな子とも仲良くできて、好き嫌いもなく、何でも食べて、積極的でリーダーシップがあって、協調性があって、勉強が出来て、優しくて、健康で・・・なんて並べてみるとあり得なそうなこと結構望んでいたりするけれど、自分が望まれたら、ゲッソリしそうだし、何より逆でも立派に豊かに生きていけますよね。きっとそういう子に育ってほしいというより、そういう子の親になりたいってことなんでしょうね。勿論私も含めて。 |
2007.5.8.発行 No.14より
| 皆さんは「がんばれ!」と言う言葉を聞いて、どんな感じがしますか?『がんばれ』『がんばろう』の時代から、『頑張らなくても いいよ』とちらほら言われるようになりましたが、何かが変った実感はあるでしょうか? 私の実感は「やっぱり、昔も今もみんなが頑張り続けている」です。親も子も、男も女も。 もうこれ以上がんばらせないでと叫びたくなる時があるくらいに。 「よくやってますね」と声をかけられたら、「ホントによくやっている、こんなに頑張っている」と自分に素直に言って上げられますか? 「そんなこと言われても、ここも、ここも足りないのに」「こんな事がやれてないのに」「他の人はやっているけど、私は全然」なんて 気持ちが湧いてきちゃうのではないかしら。実際にそういうお母さん達の言葉をよく聞きます。 「よくやっているよ」と言っても、「ウ〜ン そうかなぁ」という感じなのです。子育てや家事はやれていて当たり前、やれていないと 指摘されてしまう、というところがありますよね。でも、『やれて当たり前』と思われていることをずっとし続けることは、なんて大変な ことなのでしょう。自分がそのことが大好きで、『自分のしたいこと』であれば、感じないかもしれません。だけど、『したいこと』は百人 百様、自分で決めていいこと、心に湧きあがってくることですから。 子育てや家事をし続けていくことに、ストレスを抱えないですむ人は、たまたまいるかも、というぐらいに思っていてもいいのではない でしょうか。しかも、おなじことの繰り返し、やらないと溜まっていくことを抱えつつ、思いどうりにならない生身の子どもの相手をし続ける のは、『しんどいのだぞ』。 まぁそうやって親も成長していくのでしょうが、成長は認めて貰ってこそ、喜びになるのです。これは、親も子も同じです。こんなに、心 の成熟を求められることなのだから、『やれて当たり前』ではなく、やれていることに成長を認め、『よくやっているね』と評価されてもいい のでしょうし、「みんなで手伝うよ」と言ってもらってもいいのだと思います。親がそうされることは、必ず、親が子どもに、そうして上げられ ることにつながるのではないでしょうか。 だから、お父さん、お母さんは、『自分が頑張っている』『もっと手伝ってくれ〜』と、世界の中心で叫んでもいいのです。 がんばっているかどうかは、その人自身が決めていいのですよ。よく周りの人が決めてますけど、それって大きなお世話。自分がムリ ムリ頑張って、人にもそれをさせたがる人もよくいますが、それは自分が無理を自覚するか、止めればいいことなんですよね、ホントは。 その様に周囲に惑わされたり、自分の中に他人と比較の心があって、苦しくなってしまうかもしれないけど、自分の感じることは誰からも あーだ こーだ言われなくていいこと、ましてやこんなことを感じる自分が弱いとかダメとか、自分の感情を否定しないことです。 行動することが、がんばっていると思われがちですが、頭や心をクルクルと動かしていることも頑張っていることです。行動する頃には、 疲れちゃっていることってありませんか。又は、諦めちゃっていることもありませんか。そのことも全部ひっくるめて、『よくやっているね』 と、自分自身に言ってあげてください。そして、『よくやっていますね』と言われたら、そのことも含めて言ってくれているんだなと、素直に 喜んじゃって下さいね。それが出来ると、自然に我が子のこともそういう視線で見られるようになることうけ合い。つまり、これが出来てあ たり前、できないのがおかしい、やれるだろう、と言われてしまう子どもの辛さもわかるし、言われないことの開放感も分かるという事です。 |
2007.2.1.発行 No.13より
| 暖冬とは言われていてもやっぱり冬は冬、ついつい"寒いですね"が口をついて出てしまいます。 前回の通信では『葛藤』を取り上げました。今回は『感情のコントロール』について触れてみますね。 数年前から『キレル子』や『普通の子の犯罪』が話題になり始めました。感情のコントロールと言うと、よく感情を抑えるか 我慢する力と思われるのですが、表現する力も仲間なのです。 子どもたちは、泣いたりわめいたり、時にはひっくり返ったり、身体全体で感情を表現しているので、抑えることを 『教えなくては』と使命感に燃えてしまいがち(因みに私の場合は、しばしばもっと原始的な「ウルサイ、兎に角ダマレ」 でしたけど)ですが、2歳くらいの乳幼児期まではまず表現し、それをわかってもらうことが大切みたいです。 『ギャ〜』『ワーン』『ヤダヤダ』『○○なの〜』『ダメー』『チガウ』等々。色々表現はしつつも小さい子どもたちは、その激 しいかたまりが、いったいどうして体の中に起こってくるのか、なんなのか、どうしたら収まるのか分からないでいます。 自分の中に起こる事が分からないのは、不安なことでしょう。それを"ママがいなくなるかと思って心配だったんだね。" "自分でやってみたかったのに、うまく出来ず、くやしかったんだね""お友だちにおもちゃを取られて悲しかったんだね。" と説明を受け、分かってもらえたら安心し、表現した甲斐があったと思えるのではないかしら。子どもが不快になること、 悲しむことの経験を否定しないで、経験できたことを大切な機会と捉えて、一緒にその感情を味わって上げればいいので す。要求は通らないこともあります。それも亦経験です。通したいと大泣きしても"それは出来ないよ"でいいのです。 その時に『こんなこと言ってオニのような母かしら』とか『泣かせていたらダメな親だと思われて恥ずかしいわ』とか頭の中 をよぎったりするかもしれませんが、それは大切な自分の感情として置いといて、子どもには大泣きのピークが過ぎたら、 "お母さんに叱られて悲しかったんだよね""やりたかったのに、悔しかったんだ"と、あなたの表現したかったことは、こう いうことで、私は一応わかってるわよと返して上げ、一段落ついたら、"じゃあ、お外行こう""ブーブで遊ぼうか"と切り替 えて上げたり、"泣きやめたね"と抱きしめてあげたりすることで、子どもは気持ちの立て直しを覚えていきます。 感情が湧いて→表現して→共感や理解をしてもらって→切り替えて→立て直しをする。 それが小さい子の感情のコントロールなのかなと思います。 それは『我慢する力』ではなく、『折り合いをつける力』なのではないでしょうか。小さい頃にそれをもらっておくと、大人に なった時、共感や理解をまず自分で自分にして上げられる様な気がします。それが自己肯定感にもつながるのかなぁ。 快の感情はやりやすいけど、不快の感情は難しいですね。本当はそっちの方が奥が深いから難しいのでしょうね。 幼児くらいになると、それまで言って貰ってきたことを口に出して、自分で自分に言い聞かせて、折り合いをつけることが 始まってきます。そして段々こういう気持ちだったんだよと大人や友達に伝えられるようになってきます。 『感情が湧く』と『感情表現』の間に『折り合い』が入ってきます。感情のコントロールは、決して孤独な修行ではなく、 人の力を借りながら、心の中にまず自分の存在をしっかりと焼きつけ、そして他の人をそこに加えていく崇高な作業の様な 気がします。もし、子どもの感情を拒否したくなったり、理解できないと感じたら、自分の感情でお試し下さい。 小さくても大きくても、快でも不快でもいいから、自分の湧いてきた感情に名前や理由をつけて、存在を認め共感表現し てみるのです。(ブツブツ言ったり、書くのもOK)。行為に我慢はあるけれど、感情に我慢は必要ないのではないかしら。 自分の中に『こんな感じなんだ』という実感がると、子どもの感情を受けるときに幅がでるかも。 |
2006.11.4.発行 No.12より
| 秋も深まり、何だか急に寒くなりましたね。風邪を引いてしまった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 最近好きになった言葉があります。それは『葛藤』という言葉です。この言葉が何だか人間の証しのように感じ られたり、生きることの苦しさであると同時に面白さを表してくれたり、自分や人の力を信じる為の励みにもなって くれたり、私の中では、けっこう愛おしい"ことば"となっていま。 子どもは日々葛藤しながら自分と折り合いのつけ方を、大人に手伝ってもらいつつ学び、成長しています。 葛藤があるからこそ、発達・成長があります。 結果が出ることも出ないこともあるでしょう。でも『実』になっているんですよね。白か黒かではなく、なんだか グチャグチャとしたグレーの存在を認め、自分の中にとどめておける、そんな懐の深い人間になってみたいもの だと目下の願望。私の場合それが苦しいから人に白黒を迫ってみたり、誰かや自分のせいにしてケリをつけたく なったり、それが常なものですから。トホホ・・・。 ああでもない、こうでもないとしながらも、いつの間にかどこかに行き着いたり、パッと目の前が開けたりというこ とがあるような気がします。子どもたちの心の中はああでもない、こうでもないの真っ最中。あどけない顔をしつつも 葛藤の連続です。葛藤というのは自分の中の色々な感情がせめぎあっている状態ですよね。そんな時、正義や 常識をふりかざして自分の感情にこれはいい感情、これはあってはいけない悪い感情という評価は不要。(それは まったくもって自分に失礼なことと思えます。)どんな感情に対しても平等に「そうか、そうか、そう思っているんだ」 「わかる、わかる、ムリもないよ」「それって本当は○○ってことなんだよね」等々と尊重してあげること、自分で自 分の中にある感情に点数をつけないこと、それが自己尊重感なのかなと思います。 これって、大人は意識すれば自力で出来るかもしれないけど、子どもは自分では出来ないので、大人が言葉や態 度で表現してあげることが必要です。これは子どものいうことを全てやってあげなければいけないということとは別 物。行為はしなくてもいいし、または子どもの行為を止めてもいいのです。感情を受けとめ、そんなことを思ってもい けないというメッセージを伝えないことです。(友だちなんてキライ。貸してかげたくない。あれがほしい。いっぱい持 っていたい。あの子はズルイetc.....こんな感情もOK。もちろん大人もね。) そんなことを言っても我慢が出来ない子になるのではないかと心配になりますか。そんな心配も"あり"です。 心配の底の方に大切な、なんらかの『気持ち』が眠っているのでしょうから。 次回は(多分)この続き、感情のコントロールについて触れてみたいです。 |
2006.8.11.発行 No.11より
| 今年の梅雨は長かったですねぇ。8月にしてやっと夏到来。でもなんとなくすぐ秋がやってきそうな気配ですね。 先日家のまわりの草取りをしました。保健センターの公園の草も同様、成長の早いこと。草花同様小さな子ども達の 成長も目覚しいものがあります。でも体が大きくなったり、コミュニケーションがとれるようになったり、自分のことが 出来るようになっていったり、そんな目に見える成長と比べて心が大きくなっていくことはわかりづらいかも。 だからこそ、こころの成長を待ち、認めてもらえたら嬉しいことでしょう。赤ちゃんが初めてお友達に興味を示し、顔に さわったり、髪の毛をひっぱったりした時、「あら大変、お友達にこんなことをするなんて。」と慌てて止めたり叱ったり するのと、「もうお友だちに関心が出てきたんだ、そうだよ、お友だちだよ。」と言う思いで止めるのとでは、子どもの 感じ方が違いますよね。多分相手の子どもが感じる空気も違うでしょう。 子どもは、興味のある物にストレートに手を出します。物を取るのも、物に興味があったり、執着が出てきたり、貸せ ないのも同様、心の成長です。『たくさん持っているから貸してあげなさい、年齢が大きいんだから貸してあげなさい』は 子どもの側からすると理不尽かも。それをするのは人から決められることではなく、本当は自分で決めたいこと。お友達 との関係を作れるようになるには、様々な力の育ち、準備、時間が必要なのだと思います。 形から入ると、砂で作ったプリンのようにすぐ崩れます。遠まわりでも本物の材料で、ゆっくり中から作り上げていかないと (お互いの気持ちを言葉にしてあげること、やりとりの仕方を教えてあげること、気持ちのを切り換える時間をあげること等。) 小さな子ども達は特に、言われたことが出来るようになるためには、何回も繰り返してもらうこと、いずれ出来るようになると 信じてもらうことが必要です。大人も言われたことが心に落ちて行動として出来るようになるのに時間がかかることがありま せんか。相手との関係や心の成長が関係している場合が大人にもあります。結果はすぐにはでないのです。 人間は命が尽きるまで成長することができるので、それは一生出ないということも言えるのかな。 そこがまぁ面白いところです。 話を戻します。お友だちとの関わりの中で、大人がすぐに結果を求めたくなって子どもに迫ってしまっていたら、それは子ども の側ではなく、大人の側に理由がありそうです。相手の親にどう思われるか心配、周囲の大人たちに躾が出来ない親だと思 われないかと不安、自分も親からいい子を求められてきて、叱るのがあたりまえ、夫や周囲の人間からのプレッシャー、etc... でもそんな気持ちもいけないのでも、恥ずかしいものでもなく、大切な気持ちです。 皆色々な感情、色々な葛藤の中で生きているのですから。 そんな自分の感情に気づいたら成長の一歩。こんな風に親は子どもの成長から気づかされ、人間としての成長を促されていく のでしょう。そんな感情を持つのことがいけないのではなく、大人が自分の側に理由があるのに気づくことなく、子どもに結果を 求めてばかりいることがやっかいなことなのです。 自分の様々な感情に気づき、受け入れることが出来る親なら、子どもの感情にも気づき受け入れられるようになると思うのです。 その時々の『結果』ではなく、『経過』としての心のせいちょうを見てもらえること、それは大人も子どもも嬉しいことではないかしら。 だって、お母さん達だって経過の真っ只中なんだから。 |
2006.5.2.発行 No.10より
春は、子ども達の成長を噛みしめる季節ですね。環境が変わり、不安な思いの方もいらっしゃるかもしれませ ん。子どもの発達は、よく矛盾を乗り越えて飛躍があると言われます。矛盾を乗り越える時には、一時後戻りを したように見えたり、不安を表現することもあります。一直線、右肩上がりにはいかないものです。この曲線が 成長の醍醐味。一度落ちたり、しばらくとまったり、成長や発達には、『溜め』が大事ということです。 『這えば立て、立てば歩めの親心』と言いますね。子どもに願いや期待を持つことは、自然な親心。その『親』 の隣に『自分自身(親自身)の力と子どもの力を信じる心』を置いておく、それが子どもの成長を見守るというこ となのかなと思います。信じるということは、溜めを大切にするということです。落ちたり、とまっているように見 えても、どこかにちゃんと溜まっていて、それがいっぱいになれば、また成長があると思えること、親が見たく ない子どもの姿(友達に手を出す、すぐ泣く、だだをこねる等)にも、目をそらさないで必要なことと認めていくこ と。そして、ここがポイント! 自分の力を信じる、つまり子どもだけでなく、大人自身も同じなんだろうということに気づくことです。 親が子どもの成長を願い、信じるという一方向ではなく、私は、子どももちゃんと親の成長を願い、信じてくれて いると思っています。だからこそ子どもは、親を励まし、一方で困らせ、試し、揺さぶり、思い通りになってくれな いのです。親の中にある認めたくない感情をもあぶり出してくれるのです。子どもの頃から赤ちゃんが好きで、 大きくなったらなりたいものが、『幼稚園の先生』だった私の中に、『子どもの泣き声にイライラし、放り投げたく なる私』という、見たくない自分がいることを、子どもはつきつけてくれました。口で言っていることと、お腹の中 で思っていることが、違うイヤな自分も見せられました。 節目節目で、困ったことをし、子どもは親の成長を促してくれます。しかもちゃんと『溜め』を認めてくれて、『這 えば立て』の親心を持っていないところが、子どもの偉大なところかも・・・。もちろん私達にも、そんな偉大な 子ども時代があったこともお忘れなく。 |
| 小さい頃に、基地ごっこをしたことありますか? 基地ごっこや缶けり、校庭で遊んだオニごっこ、 男の子も女の子も混ざり合って楽しく遊びまわっていた小学校時代を思い出します。そのことを思い 出したきっかけが悲しいことに、下校途中で命を絶たれた少女の事件でした。子どもたちが常に危 険にさらされ、今以上に遊べなくなる時代がきてしまったのだと心が痛くなったのです。空間、時間 仲間、子どもたちが育つ上でどれも必要なものです。申し訳ないことに大人たちが随分と沢山子ども たちから奪い取ってしまったものでもあります。遊びを作り出せる場所がなくなり、忙しい生活と共に 時間もなくなり、安心してケンカしたり、仲良くなったり、一緒にいいことも悪いことも経験する、そんな 仲間関係も希薄になりました。 子どもって天使でもあるけれど、うるさかったり、汚かったり、あぶなかったり、めんどうだったりする 存在です。成長と共にウソもつけるようになるし、反抗もし、ずるいことを考える知恵もバッチリつきます。 何事もきれいになってしまった世の中、きれいで合理的なことを目指す大人たちにとって、時には許し がたい存在でもしれません。でも、よ〜く考えると、私たち大人も子ども時代そういう存在であり、それを 許されて大きくなってきました。世の中、見かけが『きれい』になってしまい、子ども達にとっては、迷惑な 状況かもしれませんよね。 家の中をきれいに保ちたい大人と、何でもかんでも出して試してみたくなる子ども、言う通りにして欲し い大人と、自己を育てるために反抗したい子ども、今親の目の前で、誰とでも仲良くしてほしい大人と、 人が好きだったり、コミュニケーションとりたいが故にトラブルになってしまう子ども。ステレオタイプの子を望む 大人と、他の誰とも違う自分でいたい子ども。対比しすぎかもしれないけれど、その中に見かけにこだわる 大人と、自分を作り上げていく『いのち』としての子どもの姿が見えてきます。 大人の中にも子どもの中にも、等しくある『いのち』は、昨日よりも今日、今日よりも明日と、成長したがっ ています。子どもの『いのち』を考える時に、大人のいのちのこと(生きるということ)も考えてみたいものです。 子どもって、うるさい、汚い、あぶない、めんどう、それもひっくるめて『天使』なのだと思えます。 もし、うるさい、きたない、あぶない、めんどうな存在が悪い子だと小さい頃から思い込まされて育った大人の 方がいらしたら、それもひっくるめて人間、それもひっくるめて自分は『天使』だったと、どうぞ言い聞かせて上 げてください。 グチャグチャ、ゴチャゴチャと生きることが、捨てたもんじゃないと思えたら、自分の中にも、子どもの中にも 『間』を作り出せると思います。それこそが『人』『間』かなぁ。(空間・時間・仲間、こっちの『間』も子ども達に伝 えたい!と切に思います。) |
2005.11.1.発行 No,8より
| 子どもの心がわかりますか? 人の心は、難しいですよね。子どもも大人も、同じです。大人は子どもの気持ちを頭で理解しようとするけれど、 子どもは大人の気持ちを心で感じます。これがまた鋭いのです。大人の言っていることと思っていることが違って いたら、ちゃんと思っていることを読み取ります。大人同士で子どものことを話していると、遊んでいるように見える その子が全身で聞いている(感じている)のがわかると思います。お母さんが安心しておしゃべりしている相手に対 しては、子どもも安心ができます。緊張感や安心感は伝わるんですよね。 公園やひろばで、「またお友だちに手を出すんじゃないか」「またお友だちになにかされるんじゃないか」と緊張した り、「あの子のお母さんに悪く思われるんじゃないか」「ダメな親に見られるんじゃないか」と気にしていると、お母さん の張り詰めた気持ちを感じ、おかあさんの意識がどこかに行ってしまっている、自分の感情もお母さん自身の感情も 大切にされていないと感じることでしょう。 そんな時、子どもの気持ちはキュッと縮こまってしまっているようです。 (今の時代、大人の気持ちも縮こまってしまうことが多いのかもしれませんね。) 気持ちが縮こまってしまうということは、心がかた〜くなっているということ。かたくなな心は、相手を責めたり、自分を 責めたり、内側に向いて外から自分を守ることに必死になりがち。相手を受け入れることが難しくなります。自分が大 切にされないと(してあげないと)相手を大切にしたり、受け入れたりすることが出来ないのです。 子どもが他のお友だちの持っているものを欲しがるのは当たり前。他の子を意識し始めるから起こること。そして又 自分の持っているものを貸せないもの当たり前。どちらも自然な姿です。それを悪いこと、あってはいけないことの様に 「いけません」「貸してあげなさい」としてしまうことで子どもの心は、キュッと縮こまってしまうのではないかしら。 お友だちと仲良くしなければということばかりに目を向けると、子どもの心が見えなくなってしまいそう。例えば「貸して ほしくなっちゃったね。楽しそうだもんね。終わったら貸して貰おうね」「まだ使いたいんだね、もっと遊ぶまで待ってて貰 おうね」なんて言ってあげていいのですよ。 自分の感情がたっぷり大事にされた子は、貸したり、借りたり、一緒に遊んだり、そんなことが年齢と共に自然にできて きます。そうなった時、強制された、形だけの仲良しではない、時には自分達の感情もぶつけ合える『本物』の仲良しが 誕生するのです。 これって、大人にも言えることですけどネ! |