 |
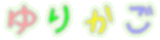 |
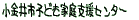 |
||
| ホーム | 『ゆりかご』って? | information | 予定表 | 関連相談機関 |
| 『ゆりかご』からお知らせ | ENJOYリポート | スタッフ便り |
| 12月講座『クリスマスお楽しみ会』リポート |
|
12月14日、少し早いクリスマスをみんなでお祝いしました。小金井でリトミックなどの活動をしている「トゥインクルキッズクラブ」のみなさんによる、お楽しみ会でした。 2階の講堂にマットを敷き詰めて、お子さんをひざに乗せたかたちで会は進みました。最初は少し緊張気味のお母さんと子どもたちでしたが、みんながよく知っている手遊びや歌を歌っているうちに、だんだん笑顔や笑い声が聞こえるようになってきました。メンバーの方たちの伴奏や歌声も素敵で、小さい赤ちゃんも引き込まれていました。 そこへトナカイとサンタクロースが登場! 子どもたちはビックリした様子でしたが、興味津々で握手してから、「あわてんぼうのサンタクロース」を歌いました。サンタさんが何なのかわからなかった子も、“とっても素敵な人”、“楽しい気持ちにさせてくれる人”、など感じてくれたのではないでしょうか。きっと心に強く印象に残ったと思います。 その後の工作では、大きなお星さまに好きな色のクレヨンで塗って、それをお面にするというのをやりました。 ちょうど講堂の隅に鏡があったので、お星さまをかぶった自分の姿を見てニンマリ。みんな、とても誇らしげに頭につけて、飛び回っていました。 最後はパネルシアターで、サンタさんに会いたくて会いたくて、寝ないで待っていようとがんばるケンタくんのお話。でもとうとうサンタさんが来る前に寝てしまって・・・でも起きてみたら、プレゼントが置いてある!・・・すると、それはさっき来てくれたサンタさんからみんなへのプレゼントでした。 メンバーの方たちの手作りと思われる、鈴のついた腕輪。 思いもかけない贈り物に、私もビックリでしたが、みんなもとてもうれしかったようです。さっそく腕に巻いて、リンリン!と鳴らしていました。 また、この日は地域のおばあちゃんが見学にいらして、ニコニコしながら子どもたちと一緒に歌ったり、手遊びしたり、とてもほんわかした空気を醸し出してくださっていました。 本当に楽しいことづくしの1時間半で、親子でリラックスできたのではないでしょうか。 (伊藤) お二人のお母さんにもリポートを書いていただきましたので、ご紹介します。 ☆1歳10ヶ月の女の子のママさんより☆ いつも「ゆりかご」を利用させて頂いているので、今回のX'mas会も、とても楽しみにしてました。 最初は娘も緊張していたのか、じっとお姉さんたちを見上げているだけでしたが、歌、お話と会が進んでいくうちに楽しんでいる表情へと変わり、空に見立てた青い布にお星さまのシールを貼ったり、大好きなサンタさんが登場したころにはすっかりリラックスしてうれしそうでした。 家へ帰ってからも、いただいた「すず」を腕につけ、作った帽子を頭にかぶり、私の歌う「あわてんぼうのサンタクロース」に合わせて何度も何度も踊ってました。 親子共々すばらしい時が過ごせて、満足した1日でした。 またこの様な体験ができたらと思います。 本当にありがとうございました。 ☆1歳4ヶ月の女の子のママさんより☆ 12月14日(火)、楽しみにしていたクリスマス会に参加しました。 トゥインクルキッズクラブの4人のお姉さんたちによる、楽しいプログラムでした。 歌あり、ダンスあり、画用紙でお星様のヘアバンドを作ったり、パネルシアターや、かわいい鈴のプレゼントも! 家の子は1歳4ヶ月でまだ難しいところもあったのですが、サンタやトナカイに扮したお姉さんたちを見て目を丸くしたりして、とても楽しそうでした。 もう少し大きなお友達は、手遊びや工作も上手にしていましたよ。もちろん大人の私たちもすごく楽しめました。 お姉さんたちの語りかけや遊ばせ方もとても上手で、今後の参考にさせていただいちゃおうと思っています。 今回は定員30組と言うことだったのですが、かなり人気が高かったようなので、次回はもっとたくさんのお友達が参加できたら良いなと思いました。 センターのスタッフの皆さん、トゥインクルキッズクラブの皆さん、素敵なクリスマス会をありがとうございました。 これからも楽しい企画、心待ちにしています。 (2004.12.28)
|
| 8月講座『パパのホリディクッキング』報告 |
|
8月7日(土)、貫井南児童館で、『パパのホリディクッキング』がありました。 夏休みでお出かけの方、夏休み前の追い込みのお仕事の方、等等の8月事情がありまして、3名の方の参加でした。日程の設定が悪くて、機会を逃してしまった方々には、申し訳なく思っています。すいません! シェフの山本さんの楽しいおしゃべりにのって、もち粉を使って、おもちとベーコンを桜の枝に巻きつけて焼く、と言うワイルドなお料理に挑戦。燻製したチーズやウィンナーを使ってのオリジナルも出来上がり、お父さん達はなかなかの腕前でした。ゆでたもち粉のおだんごをこねて、おもちになっていく様子は、さすが「お父さん」! その他に白玉だんごや燻製のやり方も伝授して頂き、盛り沢山のメニューとなりました。お味の方もバッチリ、おいしかったです。 山本シェフを始め、アシスタントをして下さった児童館のボランティアの大沢さん、シェフの奥様、そして会場と調理器具を一式貸して下さった貫井南児童館の皆様、ほんとうにありがとうございました。  (2004.08.10)
|
| 7月講座『子どもの世界』より お話:(センター長)宮澤陽子 |
|
幼い子どもたちには、私たちが忘れかけてしまった子どもの世界があります。 つい大人のものさしではかってしまって、「困ったこと」「(−)なこと」「直さなくてはいけないこと」と思いがちな姿にも、次のステップアップのために蓄えている力があります。 子どもにとっては大事な大事な意味のある姿なのです。 ダダをこねる、いたずらをする、お友だちに手を出す、グズる等々、発達にとっては必要なこと。あって当たり前なこと。 でも大人にとっては困ること、その折り合いをつけていくのには大人の心の余裕、時間の余裕が必要。 子どもには子どもの時間があって日々刻々と成長していくものの、心の中の時間はゆっくりまわっています。すぐに結果を求めず、子どもの心の中に落ちていくのを待てるといいな。 そんなお話を「表情の読み取り」「自我」「ほめる」「達成感」「トラブル」「排泄の自立」等、具体的な姿を通してお話しました。 (宮澤) (2004.07.29)
|
| 楽しかったね!親子コンサート |
|
6月29日に『ギロック・フレンズin東京』の方々による 親子コンサートがありました。 センターのお楽しみプログラムで、 何回かミニコンサートを開いて下さっている おなじみのギロックさんたち。 今回はセンターのテーマ、 『つながり』をモチーフとしての演奏会でした。 会場になった大講堂前の廊下には、30分も前から ピョンピョン跳ね回るお子さんたちの姿が・・・。 楽しみに楽しみに、心待ちにして下さっていることが 伝わってきます。 10時30分 動物のおやこメドレーで開演です。 七つの子・お馬の親子・・・と歌が進むうちに オヤオヤ、小さいおともだちが飛び入り、 歌うお姉さんのお隣で、全身でリズムをとる姿の可愛らしかったこと! OHPを使って大きな画面に映し出される絵話は、 ピアノ曲や歌・フルート・ヴァイオリンの演奏にのって ファンタスティックに運ばれます。 会場が少し暗くなって、美しい音色が次々に流れてくる中で、 お母さんたちの表情も、リラーックス。 チョコチョコっと寄って来るお子さんを、 さりげなく抱っこして歌い続けて下さるメンバーの方たちの 温かさが会場をつつんで、プログラムは進みました。 ピアノで奏でられる名曲『威風堂々』がお鍋の蓋や、 大きなプラスティックのたらいで見事に、勇壮に彩られて いくのが私には、新鮮なびっくり!でした。 楽しい歌の数々の間に織り込まれた『母の祈り』・『さとうきび畑』。 ギロックの方たちの平和への強いメッセージが込められた、澄んだ声は、 今も心に響いています。 お子さんが小さいうちは、なかなか生で音楽を聴く機会は 少ないと思うので、子どもが別室でなくその場にいて、 いっしょに楽しむことが出来る、この日のような演奏会は とても貴重に思えました。 会場の都合で今回お出で頂けなかった方、次の機会にはぜひ!! (2004.07.06)
|
| 5月親子講座 『積み木を作ろう!』 リポート |
|
(5/15(土)10:00~12:00 保健センター南側児童遊園にて) 前日まではっきりしない天候で心配しましたが、当日は青空!体を動かすと汗ばむ位の 陽気となりました。 講師の守屋辰夫さんは、センター近くで工務店をなさる傍ら、地域の子どもたちのために様々な活動をなさっています。「子ども家庭支援センター」が出来た時からも、何かの形でお手伝いをしますよ、と言って下さっていました。この講座も、とても喜んでひき受けて下さり、当日は、たくさんの角材からシート,ノコギリ、曲尺(かねじゃく)・・・と何から何まで、そしてとても素敵な笑顔もトラックに載せて駆けつけて下さいました。 この講座はお父さん方の参加が多く、講座が始まるまで何となく皆さん所在無げにしていらっしゃいましたが、守屋さんの声かけでシートを敷くなど準備に入ると、何人ずつかで相談なさりながらそこここにシートが広げられました。道具の使い方や、作る時のアドバイスを頂いた後、いよいよ積み木作りのスタート。参加の親子さんは20組。最初は砂場や滑り台で遊んでいた子どもたちも、作業が始まると、スーッとそれぞれの親御さんの所へ戻っていき,しゃがみ込んで手元を見つめたり、“ここ持ってて”と言われると長い角材を押さえたり、お父さんやお母さんの切り落とした木をやすりでこすったり、小さいながら嬉しそうに参加している姿が微笑ましかったです。かなり強い日差しに木陰を求めて移動しつつも、お父さん、お母さん方の手は休まることなく、いつの間にか、いろいろな形の積み木がずいぶん出来上がっていました。さすがに最後の方では子どもたちも、公園が楽しくなり、砂場のテーブルでごちそうを作ったり、滑り台で電車ごっこをしたり、時々けんかもしたり!ごちゃ混ぜになりながらも、大人も子どもも良い表情をしていて、”親子”講座っていいなあと思いました。 帰り際に書いて頂いたアンケートにも、「子どもの前で作る姿を見せることが出来て嬉しかった」、「また参加したい」、「もっと時間がほしかった!」・・・と参加された大人の方がとっても嬉しそうでした。 できたてほやほやの積み木とともに、開会の時に守屋さんがお話して下さった、「物を作る楽しさを味わう・物を大切にして使う心を育てる・物を活かし無駄にしない心を育てる(感謝する心)・どんなものにも役割があること」の精神(こころ)もきっと皆さんお持ち帰りになったと思います。そして、今年度のゆりかごのテーマ、「つながる−親と子が、大人と子どもが、地域が・・・」も,持って帰って頂けていたらいなあと願っています。 8月に,又、お父さん向けの講座を予定しています。いっしょにいい汗をかきましょう! (2004.06.08)
|
| 絵本の読み聞かせQ&A 4/13親子講座より |
|
会場のお母さんたちが個々に八田さんにされた質問の中から他の方にも通じるようなものをQ&Aでお伝えします。 Q1■子どもの月齢がいくつくらいから読み聞かせしたらいいですか? A;いつからでもOKです。質問された方のお子さんは7ヶ月位でしたが、「もう(始めて)十分です」と答えました。ストーリーが理解できなくても、絵を見て、きれいな言葉にふれて、ママやパパの声を聞いて、コミュニケーションをとる、絵本を真ん中にして楽しい時間をおくること。そして、絵本を読む、見る習慣を徐々につけることが大切です。決して長い物語でなくてよいのです。1ページに一行の言葉でもよいのです。 いやがる子ども、他の遊びに集中している子どもを、無理に絵本に向かわせる必要はありません。興味を示したら読んであげましょう。 Q2■めくるのを邪魔します…。 A;子どもがめくったところからまた読んでみて下さい。前に戻ればまたそこから、後ろに行ってしまえばちょっと飛ぶけどそのページの言葉を読んで下さい。そのうちにどのページにどの言葉があるのか(どのストーリーなのか)が少しずつ子どもにもわかるようになります。 Q3■なかなか落ち着いて本に向かえません。どんな本から始めたらいいですか? A;福音館あかちゃんの『がたんごとんがたんごとん』のような、擬音の繰り返しが出てくるもので、お母さんがリズムや声を変えて読んであげると子どもはきっと喜びますよ。前にも言いましたが、生活の中に絵本がある習慣を作ることが大切です。本を開くと、お母さんの声が聞こえる、何かが始まる。子どもは期待します。そのワクワク感がうれしいのです。絵本を開くときの「ワクワク感」を育ててあげましょう。 Q4■お気に入りがあって、いつでも同じ本を持ってきます。親としてはいろいろ読んで聞かせたいのに…。 A;小さいときからお気に入りがあるのはすごくいいことです。本がボロボロになるまで、飽きるまで読んであげて下さい。「それはもう読んだしね」と思うのは「記憶力」と「先入観」のある大人の感覚です。子どもの記憶力も少しずつ育ってはいますが、絵本で味わう感動や「ワクワク感」は毎回違うものなのです。「この本が好き!」という気持ちを大事にしてあげてください。 Q5■絵本を破られてしまいます。いただきものだったり、親の気に入ったものだとこちらが悲しくなります。 A;気持ちはよくわかります。けれど、どうか破られたらテープなどで張ってあげてください。厳しく叱らず、「ご本はだいじだよ〜。ママの宝物だよ〜。○○ちゃんも宝物だね。大事、大事だよ〜」と毎回言葉をかけてあげましょう。最初は本も「おもちゃ」と考えてください。1ページが硬い厚い紙でできているものを選ぶとよいでしょう。テープで貼りあわせられたぼろぼろ絵本も親と子どもの温かな時間の歴史です。大きくなってそういったルールが理解できるようになると、テープで貼りあわせた絵本、貼りあわせている親の姿がそのまま「ものを大事に長く使う」という習慣につながります。 Q6■2歳の男児。なかなか落ち着いて聞いていられません。どうしたらいいですか? A;参加型の絵本から始めてはどうでしょうか?同じ絵、動物の種類などだいぶわかってきているはずです。五味太郎さんの『たべたのだあれ』『かくしたのだあれ』(文化出版局)など。 「これはなあに?」「ウインナーッ!」「これは?」「へびっ!」「たべたの、だあれ?」「このへびさんっ!!」 ただ読み進めるのではなく、子どもとそんなふうにお話しながら読んでいくのです。 Q7■読み聞かせっていつまですればいいですか?小学校まで? A;高学年になっても、中学生になっても読んで聞かせてあげてください。自分で読めるようになっても、自分で読んでしまった本でも、読んでもらうのはうれしいものです。読書の時間と「読み聞かせ」の時間は別のものと考えて下さい。 最後に…。 絵本の世界から様々なものにふれられます。『そらまめくんのベッド』で、そら豆を知ります。そら豆を初めてむいてみた、そら豆くんのベッドである(さや)のふわふわしたところに触れてみる。「こんなベッドで寝たい!」という子、「僕のおふとんもふわふわだよ!」という子もいるでしょう。ふわふわのお布団で寝るうれしい気持ち、幸せな気持ちを親子で共有できますね。仲間のえだまめくんは夏にもなれば食卓にも出てきますね。絵本のある子育てをぜひ楽しんで下さい。 (2004.04.27)
|
| 親子講座『絵本のある子育て』4/13 |
|
絵本のある子育て 書店や保育園などで、フリーで絵本の読み聞かせをしていらっしゃる八田珠穂さんを講師に迎え、25組の親子が絵本の世界を楽しみました。3人の子育てを絵本とともに味わいつつ、他の方にもその輝く時間を知って欲しいと活動されています。読み聞かせをしていただいた本と八田さんのお話の一部をご紹介。追って、会場のお母さんたちが個々に八田さんにされた質問の中から他の方にも通じるようなものを別枠Q&Aでお伝えします。 <読み聞かせした絵本> 「さて、ここは会議室ですが、ぞうくんと散歩をしたいと思います」で始まった最初の絵本は…。 ■『ぞうくんのさんぽ』(こどものとも傑作集13なかの ひろたか, なかの まさたか 福音館書店) 最後に、重なったぞうくんやわにくんらがどっぼーんと落ちるとき、お父さんやお母さんが四つんばいになって背中に子どもさんを乗せ、お布団などに子どもさんをどっぼーんと落とすと大喜びします。雨の日にお散歩に行けないとき、晴れていて、さあ!これからお散歩!という場面で読んであげるのもいいでしょう。 「最初の子どもは天使が舞い降りてきてくれたと感動したものです。けれど、だれもがそうであるように様々な育児の大変さの壁にぶち当たりました。そんな頃に、絵本を取り入れた生活は親も子も幸せである、という一文に出会い、この幸せという言葉がこころにストンと落ちた感じがしたんですね。私は子のこと幸せになりたいと。その頃です。この本と出会ったのは」で始まった本は…。 ■『かみさまからのおくりもの』(ひぐちみちこ こぐま社) ないている赤ちゃんへのかみさまからの贈り物は「うたがすき」だったり、他の赤ちゃんも「よく食べる」や「ちからもち」などの贈り物をもらいます。「よくたべる」ことが神様からの贈り物ですよ、といわれるほど素敵なことなのだ、と親が気づかされるのです。子育て中のおかあさんへのエールかもしれません。そして、子どもも幼いながらにうれしく微かな自信をもつのかもしれません。 「あなたのこと、とっても大事に思ってるよ…。普段なかなか言えそうで伝えられない気持ちが、絵本をとおして子どもに伝わります」で始まった本は…。 ■『ぼく、にげちゃうよ』(マーガレット・W. ブラウン ほるぷ出版) 読み終わると子どもは必ずといっていいほど「ぼくのこと好き?」と聞いてきます。親としても照れてしまうことが絵本をかりてお話できます。 ★『ちびゴリラのちびちび』も。 「先ほどまで叱りつけていたのに、このような絵本を読むとこちらまでなんで怒ってしまったのかを忘れてしまいます。いい気分でお布団に入ることでいい睡眠を得られることができ良いことだと思います。就寝前に気分転換して気持ち良くお布団に入れる絵本です」。そんな絵本は…。 ■『かおかおどんなかお』(柳原良平 こぐま社) 『もこもこもこ』(谷川俊太郎 元永定正) 何十年も語り継がれる絵本の素晴らしさを…。 ■『もりのなか』(マリー・ホール・エッツ まさきるりこ訳 福音館書店) 1940年に描かれたモノクロの絵本です。一見地味なこの絵本がここまで愛されているのは、子どもの目線で描かれているからです。 (2004.04.21)
|
| 私たちの街・小金井に「子ども家庭支援センター」がオープンしました |
|
センターの開所式が6日、同センターの2階にある保健センターの講堂で行われました。稲葉市長や市会議員の方々をはじめ多くのお母さん、お父さん、子どもたちに参加していただきました。関係者を含めると100名超。「(市の中心街から)遠いので来てもらえるかな・・・」。そんなスタッフの心配も杞憂に終わりました。センター長・宮澤さんのホッとしたような笑顔が印象的でした。 オープン記念のセレモニーは、行貝ひろみさん(ともしび音楽企画)による「あったかわいわいライブ」。手遊び、歌遊び、パネルシアターなどをして楽しく過ごしました。小さい子どもは飽きてしまうかも?なんて心配もしたのです。ところが・・・。動物たちがシャボン玉をつくる(キツネさんはあぶらあげの形でしたよ〜)お話など、みんな興味津々。終わってみればグズる子も見かけなかったほど、会場が一体になって楽しんだ50分間でした。「子どもを真ん中に親と市民が手をつなごう」が合言葉の同センターらしく、ほのぼのと充実したセレモニーでした。 核家族化が進み地域で子育てをしにくくなった今、自分の子どもの成長を一緒に見守ってくれる人がいるというのはとっても心強いものです。保育園や幼稚園に通っていない乳幼児を育てるご家庭は、なかなかそういう「大人」と出会うチャンスがありません。ぜひ、小金井子ども支援センターの「常連」さんになってください。たまにしか来れなくても、スタッフはきっとおぼえていてくれるはず。あなたのかけがえのない「子ども」はわたしたち小金井の大事な子どもたちだから。 社会で子どもを育てる第一歩として、愛されるセンターになれるようスタッフ一同頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 なお、センター運営への意見、ご感想、当ホームページの感想などはトップページの「メール」をクリックして送信ください。 子育て相談は電話等でセンターへ直接お願いします。 (2004.01.07)
|
| ホーム | 『ゆりかご』って? | information | 予定表 |